|
|
16キロの棒振りでえた心友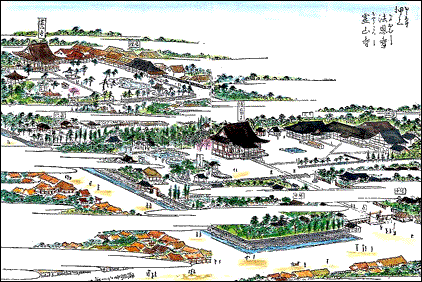 本所・押上村の法恩寺。左端の出村町の家なみの一軒が高杉道場だった。法恩寺裏が霊山寺で、本法寺はさらにその裏。 本所・押上村の法恩寺。左端の出村町の家なみの一軒が高杉道場だった。法恩寺裏が霊山寺で、本法寺はさらにその裏。「お前のおやじは、土地(ところ)の商家を軒なみに ゆすって歩き、岡場所 の女たちをしぼりぬいて、ずいぶんと阿漕(あこぎ)なまねをしてのけたものよ……(略)」 網切の甚五郎のこたえは、冷笑のみであった。二十一歳の平蔵が、ついにたまりかね、高杉道場の 同門・岸井左馬之助と井関録之助に助太刀をたのみ、 勘兵衛がひきいる無頼ども二十余人を向うへまわし、 柳島の本法寺裏で大喧嘩をやったのは、その年(明和 3年…1766)の十二月十日であった。 こっちは三人で刃物はつかわず、高杉道場で使用す る鉄条入りの振棒(ふりぼう)をもち出し、群(むら) がる無頼どもと闘(たたか)った。(文庫5[兇賊]p205 新装版215) 再読、三読目あたりまではなんの疑問も持たなかった。五読目で、 「む……」 と、『剣客商売』第2話「剣の誓約」をひらいた。25歳の秋山大治郎が、道場入門者の第1号へ4貫目(約16キロ)の振棒をあたえ、2000回は振れるようになったら剣術の稽古をつける、と宣告している。秋山父子の師である辻平右衛門ゆずりのこの振棒は、6尺(約 1.8メートル)の赤樫でつくられており先端へゆくほど太い。 このネタを池波さんは、『剣客商売』に先立つ八年前の1964年(昭和36)の『歴史読本』6月号に発表した短篇「明治の剣聖―山田次朗吉」でもつかっている。千葉県君津郡富岡村生まれの山田次朗吉が24歳のとき、師と見こんだ榊原健吉に入門を請願してゆるされるくだりがそれだ。 「およし。剣術なぞではおまんまが食えねえから……」 何度も、とめた。 しかし、次朗吉はきかない。 あまりに強情なので、ついに、 「よし。それじゃあ、そこにある振棒を十回も振って ごらん」 と、いう。 見ると、そこに長さ六尺に及ぶ鉄棒があった。目方 は十六貫余もあったというが、こんなものを、とても 次朗吉が振りまわせるものではない。 16貫といえば64キロ弱――地獄の赤鬼・青鬼の鉄棒ではあるまいし、16貫は池波さんのいつもの早とちりのような気がする。16キロ(4貫)なら筋がとおる。同短編を書くにあたって池波さんが資としたのは、山田次朗吉の高弟・大西英隆氏著『山田次朗吉伝』ほかで、その中には一橋剣友会発行の島田宏氏編『一徳斎山田次朗吉伝』もあった。後書は道場の振棒について「榊原先生時代より伝来の樫の棒がありました。長さ5尺( 1.5メートル強)、末口3寸5分位(10.5センチ強)、先太なる八角に削り手元1尺余の部分丈け丸く握れるように造られたものでした」と紹介している。榊原健吉師は老年になってもこの振棒を毎朝軽るがると振っていた。 ついでにいうと、高杉銀平は榊原健吉を彷彿とさせるが、そのことにはいまはあえて触れない。 高杉道場が横川べりの出村町に設定されたのは『江戸名所図会』の「法恩寺」の絵に基づく。寺の西側(左手)に描かれている藁屋根の家々の一軒が道場にあてられた。入江町の長谷川邸からは遠くなく、若い銕(てつ)三郎(家督前の平蔵の名)の足で横川ぞいに10分とかからない。もちろん、長谷川家が入江町に屋敷をたまわっていたというのは池波さんの創作で、史実は三ッ目は三ッ目でも南本所の菊川町で、平蔵はそこで没した。目白台は前号で明かしたように、早とちりした池波さんの創作である。 19歳の銕三郎の入門と前後して、同年で生涯の心の友となる岸井左馬之助も門人となった。下総(しもうさ)臼井(千葉県佐倉市)の郷士の息である彼の寄宿先が、なぜ押上村の春慶寺だったのか、長いあいだ疑問に思っていた。この寺は、絵はおろか記述も『名所図会』にないのだから。 日蓮宗の春慶寺へ、同じ宗派の法恩寺の住職が近隣のよしみで紹介したとも考えてみたが、春慶寺は「唖の十蔵」で捕物の舞台となる柳島の妙見堂(本性寺)に属している。それなら、臼井の岸井家の香華寺の縁によるとしたほうが自然だ。そういえば史実の長谷川家も日蓮宗だ。 『こころに残る言葉』(朝日文庫)収録「鶴屋南北の墓」と題した宇野信夫さんの一文を、〔鬼平〕教室のメンバーが見つけてきたことから推理が進展した。エッセイは、『四谷怪談』の作者・鶴屋南北の墓が春慶寺にあることを知って詣でた経緯を記している。 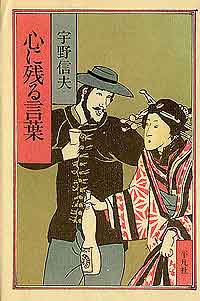 平凡社(1976) 平凡社(1976)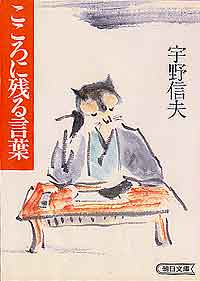 朝日文庫(1983) 朝日文庫(1983)発表は1967年(昭和42)。『犯科帳』の連載スタートは翌1968年。劇作家として出発した池波さんは、梨園に近しい宇野さんとも面識があり、一文も目にしたろうし、大先輩の南北に敬意をいだいていたことは、小房の粂八があずかっている船宿の屋号が〔鶴や〕であることからも推察できる。 それはそれとして、鬼平は、剣の技でも人格陶冶(とうや)の面でも、高杉銀平をはじめ、師の友人や同門の者たちからじつに多くのものを学んでいる。学問に身を入れたことは小説には書かれていないから、池波さんは、書物によるより実体験から学ぶタイプとして造形したかったのだろう。 鬼平のころの剣術道場は、いまの大学のゼミのクラスか部活以上の存在だったのだろう。 高杉道場で得た終生の友には岸井左馬之助をはじめ井関録之助(「乞食坊主」)や八木勘左衛門(「浮世の顔」)がいる。妻女・久栄の父親の大橋与惣兵衛(「むかしの男」)をこれに加えてもよかろう。ついでだが、平蔵の妻の名が久栄だったかどうかは別にして、大橋与惣兵衛は実際に岳父だった。 ほかにも、平蔵のことをまことの甥のように慈愛の目で指導した年長者や、平蔵が兄弟のように面倒をみた弟弟子もいた。その人たちをリストにしてみる。そけぞれが小説の中で鬼平とどんなかかわりあい方をしたか、13人中5人いいあてられたらあなたの鬼平度と記憶力は上級、と賞しよう。 リストが即座に書き出せるのは、全篇中の地名・店名・人名がすべてパソコンに記録されているせいである。 高杉道場同門者(文中に引いた人は除く) 篇名 氏名 本所・桜屋敷 谷五郎七 乞食坊主 菅野伊助 泥鰌の和助始末 松岡重兵衛 明神の次郎吉 宗円 あきらめきれずに 小野田治平 雨隠れの鶴吉 鶴吉 あごひげの三十両 野崎勘兵衛 浮世の顔 小野田武吉 霜夜 池田又四郎 おれの弟 滝口丈助 顔 井上惣助 助太刀 横川甚助  「鬼平を斬る!」記載誌 |
| ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | ||
| ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ | ||
|
|
||
|
|
||