高杉銀平師(5)
 池波さんが、山田次朗吉師著『日本剣道史』(1925刊 復刻=再建社版 1960.5.20)を口をきわめて称揚し、鬼平ファンなら、せめてその通論だけでも---とすすめているが、同書の入手はきわめて困難だし、古書店にあっても高値である。
池波さんが、山田次朗吉師著『日本剣道史』(1925刊 復刻=再建社版 1960.5.20)を口をきわめて称揚し、鬼平ファンなら、せめてその通論だけでも---とすすめているが、同書の入手はきわめて困難だし、古書店にあっても高値である。
通論の一部は、このセクション (3) (4) に引いたが、冒頭からの首要な部分を現代風の文に置き換えて掲げよう。
池波さんが高杉銀平師を造形するよりどころとした文である。
もっとも長文だし、「精神論だ」とおもう人は、きょうのところは黙視していただいてよい。
第一章 通論
わが国の歴史がはじまってよりこの方、剣戟と人びとの心とは、いささかも離れることのない関係を保ってきている。このことは尚武を推奨したためばかりでは決してない。
上古、イザナミ、イザナギの二神が蒼海を探った事蹟以後、多くの史実は剣によって事を生み、剣によって跡を垂れている。
ご注目あれ、素盞男命(すさのおのみこと)天照大神と天の安河原に誓ったとき、大神は命(みこと)が帯していた剣を噛んで御子を生み、また命は山田に邪賊を撃って霊剣を奉じたなどのほか、剣の威徳を伝える話が少なくない。
三種神器の一つとして崇敬されているゆえんたるや、げにも深いというべきである。
謹んでおもうに、三種の神宝はわが国の人道の表徴であって、玉ととなえ、鏡と呼び、剣と名づけている。
名と形は異なっているが、じつは心霊一体を示現しているにほかならない。
したがって、剣を闘争の具としてのみかんがえるならば、とんでもない誤りを生ずる。
あるときは玉となり、あるときは鏡となり、あるときは鋭い剣となってはじめて用をなすもので、これを威とし、徳とし、愛となすのである。
剣道の道は、まさに、これに基を置く。不識篇に、
「剣術は打太刀の相手を立ててやるから、微塵ほども過ちがあれば、相手はこれをとがめる。打太刀の相手に立っている人は、すなわち、生きた本箱である」
といっているごとく、その理(ことわり)をいうときは書物は諄々と説いて自分の慢心をたしなめることが、老婆の戒諭にひとしいけれど、刺撃のほうは儼竣な乃父が鞭でもってわが懈怠をはげますがごとく仮借の余地がない。
 (上泉伊勢守秀綱を描いた長編『剣の天地』(新潮文庫 1997.8.25)p94 伊勢守との決闘に向かう門人・土井甚四郎に師・十河九郎兵衛が言う。「負けるやも知れぬとおもうこころには、遅れを生ずる。ゆえに勝敗をはなれ、わが一剣に。これまでの修行のすべてを托(たく)し、伊勢守へ立ち向って見よ」)
(上泉伊勢守秀綱を描いた長編『剣の天地』(新潮文庫 1997.8.25)p94 伊勢守との決闘に向かう門人・土井甚四郎に師・十河九郎兵衛が言う。「負けるやも知れぬとおもうこころには、遅れを生ずる。ゆえに勝敗をはなれ、わが一剣に。これまでの修行のすべてを托(たく)し、伊勢守へ立ち向って見よ」)
手段は異なっていてもどちらも慈悲の念は違ってはいない。
ゆえに、いやしくも道という以上は、そのうちに仁愛の意義をふくんでいなければ道ということはできない。
文教といい武教というも、いずれも人間道義を開発するための手段であって、文そのものが即、道であるのではない。
武そのものが即、道であるのではない。
七千余巻の仏典も五車の聖経も、みんな、道へいたるための手引きである。
剣術の撃ち合いも道へ進むための手引きにほかならない。
禅学が公案を練り、師家分証の竹箆の下に印可をよろこぶのは、本来の面目を知了するからで、公案そのものは常識をもってすれば愚もはなはだしいたわごとである。
剣術の修業が一挙手、一投足、師範の咎めをうけて次第に練りすすむのは、あたかも公案を苦想する禅徒のごとく、技が熟し、術を解し、ついに心要をうるにいたれば飜然として悟り、本来の面目をとらえるのである。
 (文庫巻15『雲流剣』p37 新装版p38 鬼平が言う。「高杉先生は、江戸も外れの出村町へ、百姓屋を造(つく)り直した藁(わら)屋根の道場を構え、名も売らず、腕を誇(ほこ)らず、自然にあつまってきたおれたちのような数少ない門人を相手に、ひっそりと暮しておられたが---名流がひしめく大江戸の剣客の中でも、おれは屈指(くつし)の名人であったと、いまでもおもうている」)
(文庫巻15『雲流剣』p37 新装版p38 鬼平が言う。「高杉先生は、江戸も外れの出村町へ、百姓屋を造(つく)り直した藁(わら)屋根の道場を構え、名も売らず、腕を誇(ほこ)らず、自然にあつまってきたおれたちのような数少ない門人を相手に、ひっそりと暮しておられたが---名流がひしめく大江戸の剣客の中でも、おれは屈指(くつし)の名人であったと、いまでもおもうている」)
ここの哲理が酷似しているため、あるいは剣禅一致といい、禅の力を借りて剣道を修し、あるいは老荘の無為説を借りて剣道を行するものが出てくるのである。
右に述べたように説くと、非難の声をあげる者もいるかもしれない。
いうように、剣術が道をおさめる道具にすぎないならば、学習する必要は多分ないであろう。
精神修養に資するものは、むりに殺伐に近い剣戟を選ぶにはおよばない、古えはいうにおよばず、ましてや方今文化の競争時代に何を苦しんでこの技を必要としようぞ。
この技が古今来永続してきているゆえんは、尚古の人情と、白兵戦の場合とを推想、一面体育として適しているために学校の教科へ採用したまでである。
武器の観点からいうと、すでに時代おくれである。業の観点からいうと蠻風である。
勝敗を外にして剣の用をいうのは帽子をもって扇子の代用としてその効用を誇るにひとしい。
いっときは清風を送ったとしてももともとそのための器ではないので長期の用には耐えられない。
剣も説くところの哲理はあっても、もともとの本意はここにはない。剣にはおのずから剣の勤めというものがあるのであると。
けだし、このような反駁論があったとすれば、根本から誤解しているといわねばなるまい。
なるほど、剣の用は物を斬るためである。剣の体は護身である。
いま、その用の術を修するに、勝つことを求めるのは理の当然ともいえるが、剣戟は弓、鉄砲、そのほかの練習と異なって、自分の前に立つ相手は自分とおなじ人間である。
自分は傷つかずに敵を斬ろうとおもったときには、敵もおなじようにおもってる。
そのとき、譎詐欺瞞を弄して相手に乗ずればあるいは撃てもしようが、かならずして撃つべき場合に撃ち、乗ずべきときに乗じようとおもっても、敵もその気でいたらどうであろう。
睨みあってときをすごすか。
碁で一目を天元へ打ったのち、両者がおなじ順路におなじく黒白をならたとすると先手が一目の勝ちとなる。
これは数理のおしえるところで、剣術もこの先手をとって天元を占領する意があるのである。
ただし、棋客は対局のはじめに先後の定めがあるが、剣術はいずれが先手になるか不明である。
さらに棋客のように数理に準拠して打算することももちろんできない。
ここにいたって吾人の常識で推理してゆく術なるものは行き止まりとなる。
しかるにこの境地をふみやぶって常識外に踴り出すと、いわゆる摩訶般若という大知識がわいてきて、意行自在をえる。
 (文庫巻8[明神の次郎吉]p97 新装版p103 高杉銀平師は銕三郎と左馬之助によく言ったという。「剣術もな、上り坂のころは眼つきが鋭くなって、人にいやがられるものよ。その眼の光を殺すのだよ。おのれの眼光を殺せるようにならなくては、とうてい強い敵には勝てぬし---ふ、ふふ、おのれにも打ち勝てぬものよ」)
(文庫巻8[明神の次郎吉]p97 新装版p103 高杉銀平師は銕三郎と左馬之助によく言ったという。「剣術もな、上り坂のころは眼つきが鋭くなって、人にいやがられるものよ。その眼の光を殺すのだよ。おのれの眼光を殺せるようにならなくては、とうてい強い敵には勝てぬし---ふ、ふふ、おのれにも打ち勝てぬものよ」)
これで敵に勝つことも自由である。
ここで仁義道徳が学ばずしても了解される。
これを不可思議といわずしてなんといえばよかろう。
古人が精練の極、この界に入って一流を樹てた者が少なくない。余が道を得るに剣をいうのもここにある。
つぎに器財としては時代錯誤であり、業としては蠻風であるという説に対して答えよう。精鋭至便の武器発明がさかんな欧米になお剣闘術があるのでもわかるであろう。
たとえ、平常の知識をもって看察しても、その説が妥当でないことはあきらかになる。しかしながら、剣道がおうおうにして悪用され、古今不徳の曹漢をだしたこともこれまた多い事実である。
俗に生兵法といい、剣の道に徹底していない者ほどいたずらに自負心を増進し、わが腕力をたのみ、不正を行い、人を恐喝し、古えは人を殺傷して快をむさぼる者さえいた。
辻斬、試し斬などは、悪行のはなはだしいものである。
述べたように、剣術が大道をきわめる機縁となれば、それこそ至極の向上であるが、古来、この極に達した者は少ない。
剣聖とも剣哲ともいうべき人はおき、名人、達人もけだし少数である。針ケ谷夕雲、小出切一雲、金子夢幻、山内蓮真、寺田宗有たちは名人として称揚されている人びとであるが、ひるがえってかんがえてみると、列記の人びとはみな禅法に参じ、大悟の上で剣法と同化して妙を得たまでにとどまり、これを世用にほどこす気が薄かった。
それゆえ、これらの人びとは剣仙とでもいうべきで、後進を誘導し、人性を善化し、一般人間に与えるべき慈悲心を欠いている。
すなわち、みずからの徳性は養ったかもしれないが、仁愛惻隠の情にひややかで、社会という見地からするとむしろ無用の道具たるにすぎない。
剣道は乱世治世を分けて用をなすようではその価値はほとんど樗檪(無用の人)にひとしい。
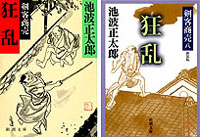 (『剣客商売』巻8[狂乱]p160 新装版p175 で、秋山小兵衛は石山甚市をさとして、「真の剣術というものはな、他人(ひと)を生かし、自分(おのれ)も生かすようにせねばならぬ」と。)
(『剣客商売』巻8[狂乱]p160 新装版p175 で、秋山小兵衛は石山甚市をさとして、「真の剣術というものはな、他人(ひと)を生かし、自分(おのれ)も生かすようにせねばならぬ」と。)
「およそ、武技は乱れた世であれば学ばなくてもいい。
平和な世に生まれた、武士という名で呼ばれる者は、武技に心身力をゆだねてこそ、その職業を忘れない一端とすべきであろう」といった古人もある。
剣道は精神をたっとぶこと、いまさらいうまでもないことだが、学んで浮き世をすて、塵をいとうがごときは本義に反している。
かつて勝海舟先生が在世中に、余らにおしえていうに、
「維新のさい、あれだけのことをやったのは、すこしばかり剣術をやったおかげさ。お前たちも精出して修業するがいい。剣術をやると万般に決断がつくよ」
と勝伯にしてはじめて剣道の応用が、幕府の衰減に際して百事を処理して遺憾がなく、江戸の地の焦熱たるをまぬがれしめただけでなくその殷富をして今日あらしめた鴻業ができたのであろうが、これらはその人を待ってはじめて用の大なるを知るので、しょせん、引例には適さない。
 霧の七郎]p37 新装版p38 で鬼平は辰蔵をさとす。「お前のすじの悪いのはわかっておる。なれど、坪井(主人)先生に日々(ひび)接することのみにても、お前のためになることだ」)
霧の七郎]p37 新装版p38 で鬼平は辰蔵をさとす。「お前のすじの悪いのはわかっておる。なれど、坪井(主人)先生に日々(ひび)接することのみにても、お前のためになることだ」)
しかし、剣道の善用も極に達したらかくのごとく活用して意義あるものとしなければ、まったくもって無用論へ帰着してしまうのである。
| 固定リンク
「083高杉銀平」カテゴリの記事
- 高杉銀平師(3)(2008.05.12)
- 高杉銀平師(2008.05.10)
- 高杉銀平師の死(2009.10.04)
- 高杉銀平師が心のこり(2009.07.19)
- 高杉銀平師(4)(2008.05.13)


コメント