池波さんが『鬼平犯科帳』に書きこんでいる、〔相模無宿(さがみむしゅく)〕の彦十の、気質、性向などを[彦十の言行録]とでも銘うって、並べてみる。
とりあえず、史実の長谷川平蔵が生きていた寛政7年(1795)の事件まで。その後は稿をあらためて---ということに。
区分は、あくまで仮のもの。
ファンなら、一読、池波さんが想定していたとおりの情景がパッと眼前に浮かぶであろう。忘れていたら、いい機会だから、もういちど文庫をお手になさって。
銕三郎との関係(かかわりあい)
「入江町の銕(てつ)さんのおためなら、こんなひからびたいのちなんざ、いつ捨てても惜しかあねえ」 巻1[本所・桜屋敷]p68 新装版p69
 「なあに、銕つぁんのためなら、いつでも死ぬよ」
「なあに、銕つぁんのためなら、いつでも死ぬよ」
と、彦十は昔なじみの気やすさで、平蔵の若きころの名をおくめんもなく口にのぼせ、
「ですがねえ、銕つぁんの旦那、たまにゃあ、奥方のお眼をぬすみ、あぶらっ濃いのを抱いて若返って下せえよ。このごろどうも銕つぁんは老(ふ)けちまって、いやだよう」 巻2[お雪の乳房]p256 新装版p269
「岸井の旦那。そのこと(若いころの銕三郎と針売り・おろくとの関係)なら、いくらでもはなしやすよ。当時はこの彦十、銕さんの腰巾着(こしぎんちゃく)というやつ、いつもぴったりおそばにくっついていたのでごぜえやすからねえ」 巻1[むかしのおんな]p278 新装版p294
「だって、おじさん。あの長谷川さまが、お盗めの助ばたらきをしたとおもうと……」
「したのではねえ。しかけたのだ。松岡重兵衛のおかげで、二人とも汚れをつけねえですんだのだ。考えても見ねえ。盗賊改メの鬼の平蔵が、むかし盗みをしたとあっちゃ、こいつはどうも、さまにならねえや」 巻7[泥鰌の和助始末]p176 新装版p185
密偵としての彦十
 縄つきとなって出て来た法楽寺の直右衛門の前へ、
縄つきとなって出て来た法楽寺の直右衛門の前へ、
「へい、お久しふりで」
と、相模の彦十が顔を出した。
「あっ……て、てめえは彦……」
「いまは、長谷川平蔵さま御手の者だよ。安くあつかってもらうめえ」
爺つぁん、胸を張ったものだ。 巻4[おみね徳次郎]p231 新装版p242
「……いや、笑っているだんじゃあねえ。あの敵討ちのはなしを長谷川さまのお耳へも入れておいたほうがよくはねえかえ。他の御門人衆はさておき、沢田さんはれっきとした火付盗賊改方の同心だ。うかつにうごかれても長谷川さまがお困りになるだろ……」 巻6[剣客]p90 新装版p96
「て、銕つぁん……」
いきなり、彦十が平蔵若き日の名を呼び、平蔵の胸をつかまぬばかりの血相となって、
「いやさ、長谷川さまよ。事のなりゆきがどうなろうと、今度は、まあちゃんの顔をたててくれねえじゃあ、このおれが、おさまりませんぜ」
と、いいはなった。
長谷川平蔵は、彦十の老顔をぬらしている泪を手ぬぐいでふいてやり、苦笑まじりに、こういった。
「彦よ。むかしむかしの本所の銕のころから、このおれのすることに、お前、一度でも愛想(あいそ)がつきたことがあったかえ、どうだ」 文庫巻4[狐火]p146 新装版p154
「あの二人なら、きっと出来るとおもったのだ。それも彦十、三十をこえたおまさが、何年も男の肌から離れているのは、こいつ、女の躰のためによくねえことだと、おもったからさ」
「けれど銕……いえ、長谷川さまよ。おまさはむかしから、お前さんに惚れこんでいて……」
「ばかをいうな……」
「へ……」
「盗賊改メの御頭が、女密偵に手をだせるか」 巻9[鯉肝のお里」p80 新装版p84
 彦十が、血に染(そ)んだ土間から、小さな珊瑚玉の簪(かんざし)を拾いげ、平蔵へ見せた。
彦十が、血に染(そ)んだ土間から、小さな珊瑚玉の簪(かんざし)を拾いげ、平蔵へ見せた。
「長谷川さまよう。この簪を。おぼえていなさいますかえ」
「む……いま、おもい出した」
「お前さまが、五両の餞別といっしょに、お百へくれてやった、さんごのかんざしだ。この、かんざしを両国まで買いに行ったのは、この彦十だったっけ……」 巻11[密告]p213 新装版p222
「へへえ、へへえと感心してばかりいねえで、おらにもいっぺえ、もって来てくんなよ」
「よし、よし」
「こいつ、大人(おとな)ぶった口をきくねえ。むかしは、おめえをおぶってやって、小便をひっかけられたこともあるんだぜ」
「どうも爺つぁんと長谷川さまには、かなわねえや」 巻12[いろおとこ]p13 新装版p13
彦十の人生観
「さすがに銕つぁんの旦那だ。ねえ。夜鷹を殺した野郎には御詮議(ごせんぎ)がねえのですかい。そ、そんなべらぼうがあってたまるかい」 巻4[夜鷹殺し]p279 新装版p293
「ときに、彦十」
「へ、へい……」
「お前が、むかし、金をつけて、千住の煮売り屋へ押しつけた女は、いま、どうしている?」
「よそながら、ときどき前を通って見かけやすがね。へえ……へえ、もうあれから四人も子を生んで、いい婆さんになっておりやすよう」
「いい気なものよ」 巻10[むかしなじみ]p214 新装版p226
長谷川平蔵が、これまでのことをざっと語って、
「その、今戸の井坂宗仙という町医者のことを探ってくれ。あのあたりには、いくらも、お前がくびを突っこむところがあるはずだ」
金を紙につつんで彦十へわたし、
「一夜の酒手(さかて)には、それで充分だろうよ」
「へへっ、すみませんねえ、銕つぁん。おらあ、小づかいをもらうのが大好きだ」 巻11[毒]p243 新装版p253
彦十 ここにいる六人は、みんな、いい機会(おり)さえありゃあ、むかし取った杵柄(きねづか)というやつで……お盗めの見本を世の中に見せてやりてえと、こうおもっているのさ。 巻12[密偵たちの宴]p162 新装版p171
肋骨(あばらぼね)の浮いた、渋紙のような肌をした老体を隅に沈めながら、彦十が、
「むかし、上方(かみがた)の、高窓(たかまど)の久兵衛(きゅうべえ)お頭(かしら)のところで、嘗役(なめやく)をしていた利平治(りへいじ)というのが二人連(づ)れで、この宿屋へ入る(へえ)って来ましたよ」 巻13[熱海みやげの宝物]p10 新装版p10
平蔵が振り返って見ると、六郷川の岸辺に馬蕗の利平治が両膝をつき、こちらへ向って合掌しているではないか。
渡し舟から下りる人、乗る旅人が、利平治をながめ、ざわめいている。期せずして、人びとの視線が平蔵と彦十へあつまるものだから、
「へ、へへ……鬼平大明神でごぜえますね」
彦十が鼻をうごめかすのへ、
「つまらねえことをいうな」 巻13[熱海みやげの宝物]p52 新装版p53
目利きの彦十
(牢を出され、彦十の長屋へ寄宿して、大工の万三を探している五郎蔵について訊かれ)
「毎日、いろいろ服装(なり)を変えて出て行きますぜ。あの人はでえじょうぶだ。もう。すっかり、銕つぁんの旦那におそれ入zwまさあ」 巻5[深川・千鳥橋]p24 新装版p25
「痔もちの盗人か、それはおもしろい」
「それでね、銕つぁん。野郎、なかなかふんぎりがつかねえようだ」
「ほほう……」
「ありゃあ何だね、牛尾の太兵衛のところにいた盗人だというけれど、ろくな盗めはしていませんぜ。せいぜい、田舎の盗人宿の番人ぐれえなところで」 巻9[泥亀]p115 新装版p121
「お、彦十。どうだ、見おぼえがあったか」
といった平蔵の口もとが微(かす)かに、渋い笑いをたたえていた。
「あの顔は、殿さま小平次そっくりというやつで……」
彦十がいうのへ、平蔵はこういったものである。
「おれも、いま、その男の名をおもい出したところだ」 巻11[密告]p190 新装版p198
彦十の女性観
「まあちゃん。三十をこしてもお前はまだ、むすめみてえな気もちが残っているのだなあ」
「女は、みんな、そうなんですよ」 巻6[狐火]p133 新装版p141
「男と女の躰のぐあいなんてものは、きまりきっているようでいてそうでねえ。たがいの躰と肌が、ぴったりと、こころゆくまで合うなんてことは、百に一つさ。まあちゃん。お前と二代目は、その百に一つだったんだねえ」 巻6[狐火]p134 新装版p142
「長谷川さまは、先代・狐火の妾のお静さんとできちまった。それをまた、まだ十二か十三のおまさが、小むすめのやきもちをやいてねえ」
「そんなことが、あったのか---」
「とぼけちゃあ、いけませんや」
「あのころの、おまさは、まだ子どもよ」
「女の十二、三は、躰はともかく、気もちはもう、いっぱしの女でござんすよう」 巻6[狐火]p157 新装版p165
「色の浅ぐろい、痩せた女だねえ、おじさん」
「む、ああいう女(の)にかぎって、色のほうもすさまじいのだよ」 巻8[白と黒]p225 新装版p237
「とんでもねえ。ああいう女と男は、たがいに顔がきれいだとか様子がいいとかいうのではねえ。天性(てんせい)そなわった色の魔物が、躰の中に巣食っているのでござんしょうよ」 巻8[白と黒]p227 新装版p239
「小むすめの勘は、するどいものだ」
「ところが女も、年を食うにつれて、間がぬけてきやすからねえ」 巻12[二つの顔]p224 新装版p235
【参照】[相模(さがみ)〕の彦十] (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
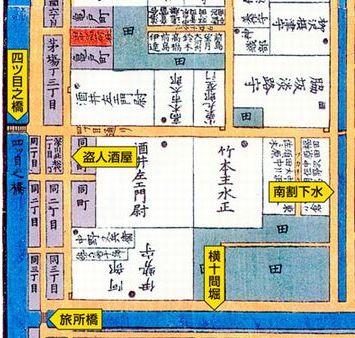

 水しぶきの向こうから、鹿が一頭、姿をみせた。
水しぶきの向こうから、鹿が一頭、姿をみせた。 「なあに、銕つぁんのためなら、いつでも死ぬよ」
「なあに、銕つぁんのためなら、いつでも死ぬよ」 縄つきとなって出て来た法楽寺の直右衛門の前へ、
縄つきとなって出て来た法楽寺の直右衛門の前へ、 彦十が、血に染(そ)んだ土間から、小さな珊瑚玉の簪(かんざし)を拾いげ、平蔵へ見せた。
彦十が、血に染(そ)んだ土間から、小さな珊瑚玉の簪(かんざし)を拾いげ、平蔵へ見せた。
 そうおもいながらも、便利な使い走りを兼ねた狂言まわしという見方を永いあいだ、ふっきることができなかった。
そうおもいながらも、便利な使い走りを兼ねた狂言まわしという見方を永いあいだ、ふっきることができなかった。

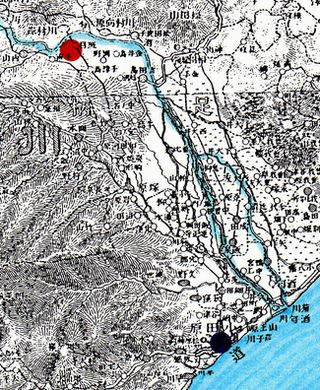
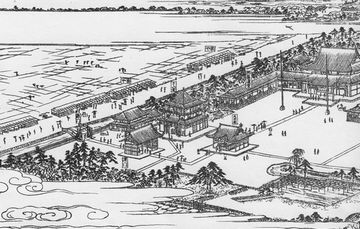


最近のコメント