亡父・宣雄の三回忌(3)
「腹の中の子に、障(さわ)りはないのか?」
自分の位置に枕を置き、するりとはいってきた久栄(ひさえ 23歳)の腹に、掌(たなごころ)をあてて平蔵(へいぞう 30歳)がたしかめた。
亡父・宣雄(のぶお 享年55歳)の三回忌の供養が終わり、親類たちも引きあげ、辰蔵(たつぞう 6歳)、初(はつ 3歳)も寝入り、平蔵もほっとして横になっていたときであった。
「お隣りの松田さまの於千華(ちか 40歳)さまから、5手ほど教わっております。今夜はその3で---」
「その5までも、あるのか? しかし、於千華どのは、新三郎どの一人しか産んではいないのに、ずいぶんと究めたものだな」
「このことが好きおなごなら、とことん究めます」
「久栄、お前は好きなのか」
「はい。好きで好きでたまりませぬ」
平蔵の手首をとり、指をみちびいた。
しぱらく、お互いの指でじゃれあっている。
「ご本家の於佐兎(さと 60歳)大伯母さまが、そっとお洩らしなりましたが、あちらは、いまでもだそうでございますよ」
「いつの間に、そんな話を交わしたのだ?」
「お水をご所望で、調理場へごあんないしたときに---」
「油断も隙もあったものではない」
「於佐兎大伯母さまは、お姑さまのことを、脇腹を断ちきったとお誉めでしたが、お舅どのはずっと、お姑さまだけでしたのでしょうか?」
「久栄は、どう見ている?」
「長谷川家の血---というより、武家方は、子が多いほどよろしいのですから---」
「長谷川家の血?」
「よそに、お子だけはおつくりになりませぬよう。銕(てつ)さまのお子は、私が、もういい、といわれるほど産みますゆえ---」
息づかいが荒くなってきていた久栄が、薄い上がけの布団をはぎすて、寝衣の裾をからげ、うつ伏せになるとひざで支えて尻をあげ、
「その3でございます」

(国芳『江戸錦吾妻文庫』部分 イメージ)
平蔵がその3を終え、久栄にかぶさった。
横になって向きあい、互いの躰をゆっくりと撫ぜあいながら、
「お舅どのは、このことよりも、もっとご興味のあることがおありになったのでしょう」
「いや。わしはそうはおもわぬ。わしが生まれ前に、ことが過ぎたので、飽いたのであろうよ」
「銕(てつ)さまは、まだ、お飽きになりませぬか?」
「その4と、その5を試み終えれば、飽きてくるかもな」
「では、明晩、その4を---」
「急ぐには及ばぬ」
「お、ほほほ。本音がでました」
「あ、はははは」
「お飽きになるのを、いつまででもお待ち申しあげております」
「よい、三回忌の供養であった」
「いいえ、1回きりでございました。三回忌なら、その4、その5を終えませぬと---」
「わかっておる」

 滝川政次郎先生『長谷川平蔵 その生涯と人足寄場』(朝日選書 のち中公文庫)は、京都在住の牢人・岡藤利忠が書いた『京兆府尹記事』を引き、宣以の機転と利発のあかしとされている。
滝川政次郎先生『長谷川平蔵 その生涯と人足寄場』(朝日選書 のち中公文庫)は、京都在住の牢人・岡藤利忠が書いた『京兆府尹記事』を引き、宣以の機転と利発のあかしとされている。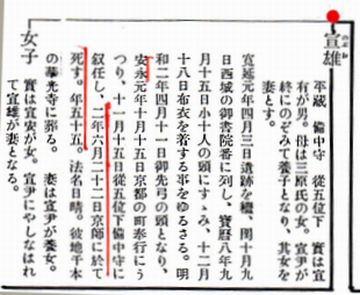
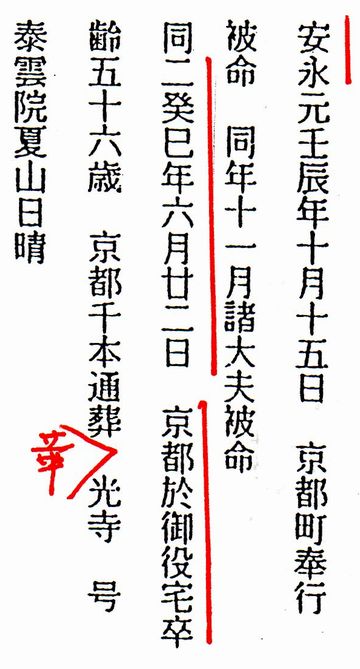

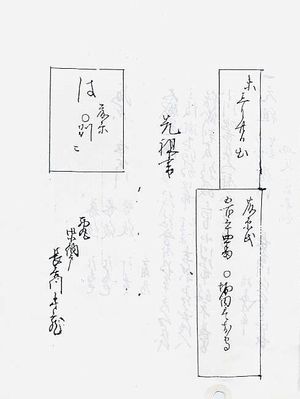
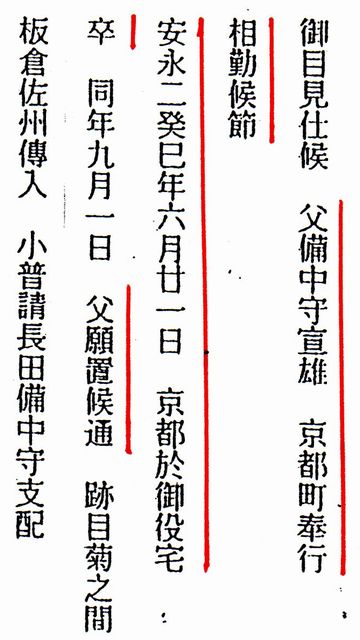

最近のコメント