「もう聞くことはないのか!」
佐藤隆介さんは、ある時期、池波さんにぴったりつき添って、その言行を書き留めた貴重な人である。
池波ファンにとっては、池波さんの素顔に、もう一歩近づく手だてといえようか。
ちょっとオーヴァーにいうと、辞書製作者の碩学サミュエル・ジョンソンと、その言行を記録したジェイムズ・ボズウェルの関係に似ている。
 佐藤隆介さんのお仕事の一つに『男のリズム』(角川文庫 1979.12.20)の巻末解説がある。
佐藤隆介さんのお仕事の一つに『男のリズム』(角川文庫 1979.12.20)の巻末解説がある。
いや、佐藤さんは、文庫になった池波さんの小説やエッセイの多くに、丁寧な解説文を寄せているから、とりたてていうほどのことはないのだが、『男のリズム』のそれは、ちょっと調子が違う。
冒頭に、自分の生の声をぶつけているのだ。
電車の座席で、マンガ雑誌を読みふけっている若者に、
「きみは明日死ぬかもしれないんだよ---」
と言ってみてやりたい衝動をおぼえるというのだ。
人間は、生まれたときから死へ向かって日々歩いている---が、池波哲学の一つであることは、ファンならみんな知っている。
佐藤さんは、それをじかに池波さんの口から聞いている生き証人である。
佐藤さんの哲学の一部になっているから、若者に言ってやりたくもなるのであろう。
『男のリズム』の[最後の目標]という章に、
私の師匠・長谷川伸(はせがわしん)は、生前、よく私に、
「君、もうすぐに、ぼくはあの世へ行っちまうんだよ」
と、いわれた。
これは、御自分が生きている間に、もっと聞きたいことはないのか、と、いうことなのだ。
昭和38年6月11日に長谷川伸師が逝き、すぐあとの追悼号ともいえる『大衆文芸』(1963年8月号)に、池波さんは[先生の声]と題し、こうも書いている。
「君ねえ、ぼくなんか、いつ、ひょっくりと死ぬかも知れないんだよ。聞くことがあるんなら今のうちだよ」
にこにこと言って下さっているうちは、よかったが、対座して話題につきると、
「もう聞くことはないのか!」
きびしく、言われた。
これを書いたとき、池波さんは40歳。長谷川伸師の享年79。
40歳になっても教えを乞える師がいるなんて、人生の幸せの時ともいえ、うらやましい。
長谷川伸という師は、自分の体験したことであれ、温めている小説のテーマであれ、門下の人には惜しむことなく明かしたと、エッセイ『石瓦混肴』にある。
長谷川伸師が聖路加病院の病室で亡くなったとき、池波さんは玄関ホールまではかけつけたが、病室へは、あえて入らなかったという。
師の尊顔は、生き生きしていたときの思い出だけで十分---と決めていたからだと。
そうそう、J・ボズウェルが書きとめたS・ジョンソンのこんな言葉が、『オクスフォード引用句辞典』に入っていて、英語圏の人はよく、引用する。
「ロンドンに飽きたら、人生に飽きたに等しい」
ぼくも、〔ロンドン〕を〔『鬼平犯科帳』〕に置き換えて、ときどき使っている。

 [2-3 女掏摸(めんびき)お富〕は、『オール讀物』1968年(昭和43)10月号に発表された。
[2-3 女掏摸(めんびき)お富〕は、『オール讀物』1968年(昭和43)10月号に発表された。 ネタの出所は、三田村鳶魚[五人小僧]( 『泥棒づくし』河出文庫 1988.3.4)の
ネタの出所は、三田村鳶魚[五人小僧]( 『泥棒づくし』河出文庫 1988.3.4)の 〔新鷹会〕〔二十六日会〕が池波正太郎という作家の成長に、どれほど資したか、想像している。
〔新鷹会〕〔二十六日会〕が池波正太郎という作家の成長に、どれほど資したか、想像している。 1956年下期 [恩田木工] 『大衆文芸』
1956年下期 [恩田木工] 『大衆文芸』 そこのところを察していたらしい長谷川伸師とのあいだに、こんな会話があったことを、未収録エッセイ第4集『新しいもの 古いもの』(講談社 2003.6.15)の[亡師]に書き残している。
そこのところを察していたらしい長谷川伸師とのあいだに、こんな会話があったことを、未収録エッセイ第4集『新しいもの 古いもの』(講談社 2003.6.15)の[亡師]に書き残している。

 300本近くある長谷川伸師の脚本のうち、『瞼の母」『関の弥太っぺ』『沓掛時次郎』や『一本刀土俵入り』 は、地方の劇場や旅回りの劇団で、とりわけ多く上演されていると、橋本正樹さんが長谷川伸師の脚本6本を収録のちくま文庫『沓掛時次郎・瞼の母』(1994.10.24)の巻末解説で明かす。
300本近くある長谷川伸師の脚本のうち、『瞼の母」『関の弥太っぺ』『沓掛時次郎』や『一本刀土俵入り』 は、地方の劇場や旅回りの劇団で、とりわけ多く上演されていると、橋本正樹さんが長谷川伸師の脚本6本を収録のちくま文庫『沓掛時次郎・瞼の母』(1994.10.24)の巻末解説で明かす。 すこしそれるが、2度にわたって紹介した、長谷川伸師のたくましい太ももと池波さんの体格のこと。
すこしそれるが、2度にわたって紹介した、長谷川伸師のたくましい太ももと池波さんの体格のこと。 書庫の片隅から『青春忘れ物』(中公文庫 1970.8.10)が出てきた。
書庫の片隅から『青春忘れ物』(中公文庫 1970.8.10)が出てきた。 手元の中公文庫の長谷川伸『日本敵討ち異相』は、1974年(昭和49)5月10日に初版が出ている。
手元の中公文庫の長谷川伸『日本敵討ち異相』は、1974年(昭和49)5月10日に初版が出ている。 直木賞を受賞した1960年(昭和35)には、歌舞伎『加賀見山旧錦絵(かがみやまこきょうのにしきえ)』に材をとった[実説鏡山-女仇討事件] (PHP文庫『霧に消えた影』に収録)と、[うんぷてんぷ](角川文庫『仇討ち』に収録)を執筆。
直木賞を受賞した1960年(昭和35)には、歌舞伎『加賀見山旧錦絵(かがみやまこきょうのにしきえ)』に材をとった[実説鏡山-女仇討事件] (PHP文庫『霧に消えた影』に収録)と、[うんぷてんぷ](角川文庫『仇討ち』に収録)を執筆。 【つぶやき】[うんぷてんぷ]で、ヒロインの娼婦お君が、逃亡かたがた熱海へ湯治としゃれたとき、〔本陣今井半太夫〕の前を通って本町へ。
【つぶやき】[うんぷてんぷ]で、ヒロインの娼婦お君が、逃亡かたがた熱海へ湯治としゃれたとき、〔本陣今井半太夫〕の前を通って本町へ。
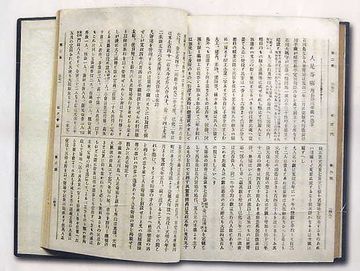
 これを確かめるために、平岩弓枝さんの許しをもらって長谷川伸師の書庫へ入り、3冊に合本・装丁された『江戸会誌』を見つけたときは、われしらず、快哉を叫んだ。
これを確かめるために、平岩弓枝さんの許しをもらって長谷川伸師の書庫へ入り、3冊に合本・装丁された『江戸会誌』を見つけたときは、われしらず、快哉を叫んだ。


最近のコメント